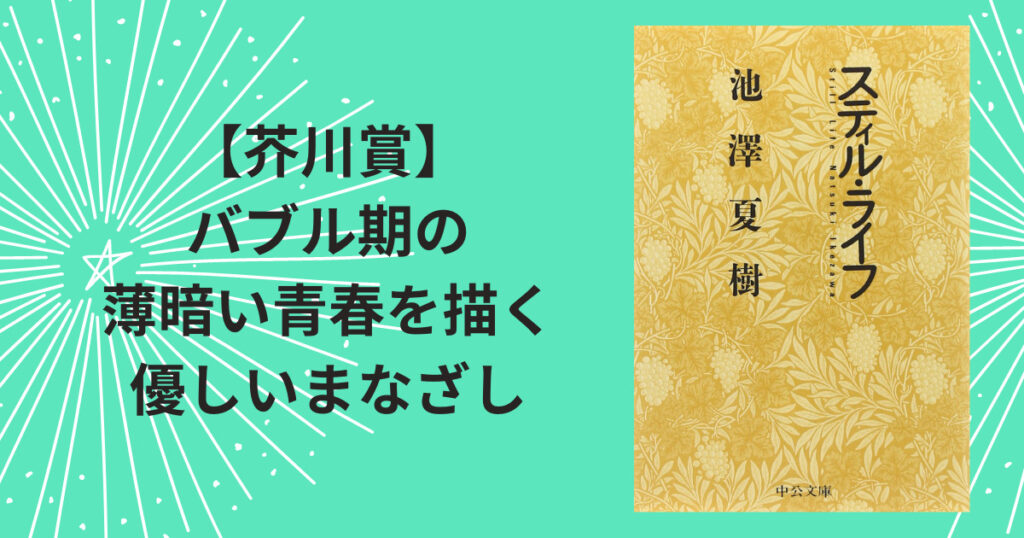
池澤夏樹の作品を読んでいると、ふっと浮かんでくる光景がある。それは小学校のとき、誰もいない図書室でぼんやり眺めていた古い本棚とか、いつか閑静な住宅街を散歩している時に目に入った、昭和期に建てられたであろう大きな空き家とか。実家の窓際に昔から飾られていた、なんともバブル期らしい作りの船の置物とか。
平成生まれの自分が、実際に通ってきたわけではない、しかし身の回りで息をし続けていたバブルという気配を、わたしはなぜだか懐かしいと感じ、愛着を持っている。ときどき、本当はバブルを生きてきたのではないかとさえ思ってしまう瞬間さえある。
「スティル・ライフ」が芥川賞を受賞した1988年は、山下達郎のGET BACK IN LOVE、中森明菜のTATTOO、工藤静香のMUGO・ん…色っぽい等々、そうそうたる名曲たちがリリースされた年だ。今考えるとありえないくらいに華やかで、文化、遊び、すべてが豊かな時代だったのだろうと思う。
そのような時代の空気の中で、この「スティル・ライフ」はどこか陰りを帯びた世界観が描かれる。バブルという時代の感覚は確かに読み取れるのだが、「ぼく」や佐々井はザ・80年代なイケイケのキャラクターとしては描かれていない。それがこの作品の魅力であり、わたしたちを懐かしいけれども、全く違う世界へと連れて行ってくれる。
社会や他者との距離感で作られている世界とは別に、自分という世界があることに気づかせてくれる。
登場人物たちが世界を見る視点が、何にも媚びることなく、シンプルで美しい。
風景描写が詩的で秀逸。
池澤夏樹
池澤 夏樹 (いけざわ なつき)1945年7月7日 北海道帯広市生まれ。父は小説家の福永武彦。
小説、詩、評論、翻訳など幅広く手掛けている。70年代、ギリシャに三年間滞在するなど、旅や移住が多い。こうしたライフスタイルや、大学で専攻した物理学の知識が彼の作品の特徴となっている。
『夏の朝の成層圏』(1984年)
『スティル・ライフ』(1988年)中央公論新人賞、芥川龍之介賞
『マシアス・ギリの失脚』(1993年)谷崎潤一郎賞
『花を運ぶ妹』(2000年)毎日出版文化賞
『光の指で触れよ』(2008年)
『静かな大地』(2004年)親鸞賞、など。
『スティル・ライフ』
- 出版社 : 中央公論新社 (1991/12/10)
- 発売日 : 1991/12/10
- 文庫 : 216ページ
- ISBN-10 : 4122018595
- ISBN-13 : 978-4122018594
あらすじ
ある日、ぼくの前に佐々井が現れてから、ぼくの世界を見る視線は変って行った。ぼくは彼が語る宇宙や微粒子の話に熱中する。佐々井が消えるように去ったあとも、ぼくは彼を、遥か彼方に光る微小な天体のように感じるのだ_科学と文学の新しい親和。清澄で緊張にみちた抒情性。しなやかな感性と端正な成熟が生みだした、世界に誇りうる美しい青春小説の誕生。中央公論新人賞、芥川賞、受賞作。
染色工場でアルバイトをしている「ぼく」は、大ポカ(今ではあまり聞かない言い方だけれど、なんか良い)をやってしまう。それを助けてくれたのが佐々井だった。「ぼく」はお礼に彼を飲みに誘う。
「ぼく」は生きていく上で何をすべきなのかが分からない。アルバイトをしながら、何かするに値することを探している。一方で佐々井は、長い人生をかけて取り組む対象を、すでに見つけてしまったという印象を「ぼく」に与えた。
「ぼく」は佐々井の「世界の全体を見る視線」で語る話に夢中になる。
そんなある日、佐々井からある秘密を打ち明けられてーー
感想
「孤独」とは何かーー世界を見る視線を変えてみる
詩人の谷川俊太郎が、テレビだったか本だったかでこんなことを言っていたのを、いつかの自分の日記に走り書きしていた。ひとの孤独は、「人間社会内孤独」と「自然宇宙内孤独」が、意識するしないにかかわらず、ダイナミックに重なり合っている、と。
佐々井は、社会で人と関わる中で「人の手の届かない部分がある」という。
大事なのは、山脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界と、きみの中にある広い世界との間に連絡をつけること、一歩の距離をおいて並び立つ二つの世界の呼応と調和をはかることだ。
たとえば、星を見るとかして。
「スティル・ライフ」
この佐々井の語る二つの世界は、谷川俊太郎のいう二種類の孤独と近いのではないかと思った。
外の世界だけに目を向けていると、次第に自分を見失ってしまうし、自分の中の世界だけに生きれば、現実社会で生活していくのは難しい。両者のバランスを保つことをの心地よさを、佐々井は「ぼく」に伝える。
主人公「ぼく」や佐々井の、何者にも媚びることなく、シンプルな考え方
ときに世界は、みなが同じ方向に、同じ速さで生きることを強いる。「ぼく」はそれに抵抗しながらも、迷いながら日々を送っている。それが佐々井と出会ったことで、
どんなことになってもぼくを巡る世界はぼくを傷つけることができない。
「スティル・ライフ」
という自信を持つようになる。
ある日突然、佐々井が現実的な顔を覗かせ、金銭的な相談を持ち掛けられても、「ぼく」は冷静に受け入れる。佐々井の方も、「ぼく」の達観したものの考え方に、安心したのだろう。
そしてすべてが流れるように終わったあと、佐々井はいなくなり、「ぼく」の生活は淡々と続いていく。
二人の関係性は、まるでお互いが遠くの星であるかのように、ちょうど良い距離感を保っている。その心地よさ。
こうした「ぼく」や佐々井の何者にも媚びない、シンプルな生き方は、今でこそ、ようやく広まりつつある考え方だと思う。バブルという、物質的なものの大切さが重視される世の中だったころから、30年と少しが経った。もし二人が現実に生きていたら、今、どんな風に生きているのだろう、とぼんやり考えてしまう。
詩的な風景描写
スティル・ライフとは、静止画の意味。佐々井と出会った「ぼく」は、流れ続ける世界の中で、一歩立ち止まって世界を見渡す。彼女とも別れ、先の分からない日々の中で、ひとり真冬の海へ出かけたときのワンシーン。
雪が降るのではない。雪片に満たされた宇宙を、ぼくを乗せたこの世界の方が上へ上へと昇っているのだ。静かに、滑らかに、着実に、世界は上昇を続けていた。ぼくはその世界の真中に置かれた岩に座っていた。岩が昇り、海の全部が、厖大な量の水のすべてが、波一つ立てずに昇り、それを見るぼくが昇っている。雪はその限りない上昇の指標でしかなかった。
「スティル・ライフ」
この美しいシーンに、物語のすべてが詰まっているように思う。わたしたちは、ページをめくってこの場面に出会うたびに、何度も救われ、温かな心を取り戻すことができるだろう。
まとめ
生まれる前の時代の気配を、なぜだか懐かしいと感じてしまう。それがずっと不思議だった。人はふとした時に、「ぼく」や佐々井のように、自分の中に広がる遥かな世界を見ているのだ。
このブログは、カモメちゃんが「本はファッションの一部」を座右の銘に、自分らしさを伝えるツールとしての、「本」の楽しみ方を紹介する記事を書いています。面白い!と思ってくださった方は、ぜひ、ブックマークしてくださいね!