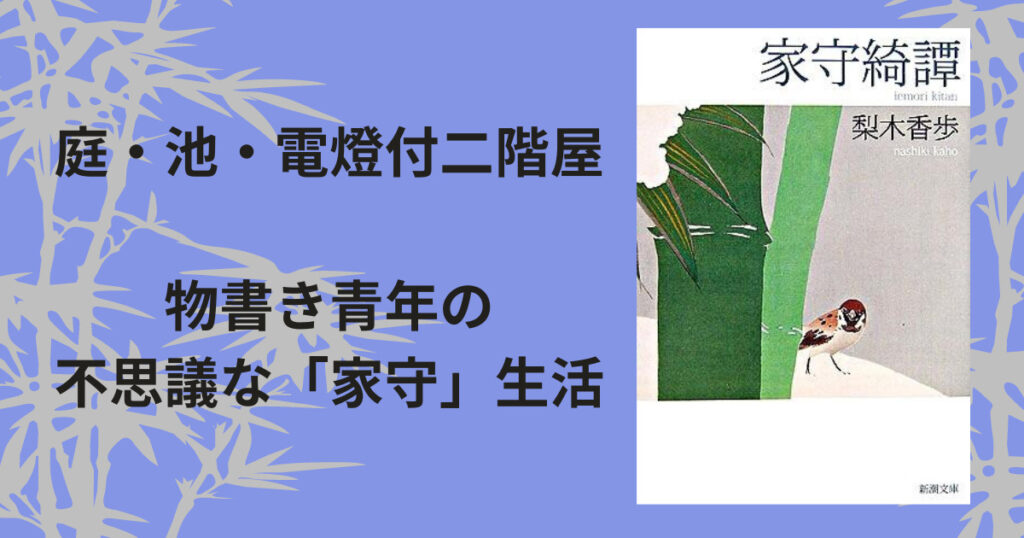
百年、と聞くと多くの文学好きがパッと思い浮かぶイメージがある。
それは夏目漱石の、こんな夢を見た、という言葉から始まる「夢十夜」のワンシーン。仰向けに寝た女がもう死にますと言い、枕元に座っている主人公に、「百年、私の墓の傍に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」そう言い残して目を閉じる。
本書「家守綺譚」(いえもりきたん)は、今からほんの百年すこし前の物語である。舞台は京都、山科辺りと思われる。
主人公、綿貫征四郎は駆け出しの物書き。湖で亡くなった友人、高堂の実家に「家守」として住むことになる。庭、池、電燈付きの二階家。
そこでは庭に植わっているサルスベリに懸想されたり、河童や小鬼、不思議なものたちが当たり前にそばにいたりする。それを綿貫もあわてることなく受け入れて、四季折々の風景が流れていく。
不思議なことが日常の一部だった、古き良き時代にタイムスリップした感覚になれる。
あらゆるものを自然に受け入れる綿貫、飼い犬のゴロー、数々の不思議なものたち、どのキャラクターにも作者の愛が感じられる。
風景や草花の描写が美しく表情豊かで、想像しなくてもスッと入りこんでくる感覚を味わえる。
梨木香歩
梨木香歩(なしき かほ)1959年(昭和34年) - 、鹿児島県生まれ。
同志社大学卒業後、イギリスに留学。
『西の魔女が死んだ』で日本児童文学者協会新人賞、新美南吉児童文学賞、小学館文学賞を受賞
『裏庭』で児童文学ファンタジー大賞を受賞
『家守綺譚』で本屋大賞3位入賞
『沼地のある森を抜けて』で第5回(2005年度)センス・オブ・ジェンダー賞大賞を受賞。同作品で第16回(2006年度)紫式部文学賞を受賞
『渡りの足跡』で第62回(2010年度)読売文学賞随筆・紀行部門を受賞
ほかに『村田エフェンディ滞土録』(2004年)、『ピスタチオ』(2010年)、『海うそ』(2014年)など。
『家守綺譚』
出版社 : 新潮社 (2004/1/30)
発売日 : 2004/1/30
単行本 : 155ページ
ISBN-10 : 4104299030
ISBN-13 : 978-4104299034
あらすじ
庭・池・電燈付二階屋。汽車駅・銭湯近接。四季折々、草・花・鳥・獣・仔竜・小鬼・河童・人魚・竹精・桜鬼・聖母・亡友等々々出没数多...本書は、百年まえ、天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねてる新米精神労働者の「私」=綿貫征四郎と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。―綿貫征四郎の随筆「烏蘞苺記(やぶがらしのき)」を巻末に収録。
物語は28編から成り、それぞれのタイトルがヒツジグサ、白木蓮、檸檬、など、植物の名前になっている。読み進めるごとに、物語の世界に生い茂った草花の匂いやざわめき、季節の移ろいが生き生きと感じられる。
感想(ネタバレなし)
サルスベリに惚れられる綿貫の魅力
綿貫は駆け出しの物書き。学生時代の友人で、湖でボートを漕いでいる最中に行方不明になった高堂の実家に、「家守」として住むことになる。
ある夜、床の間の掛け軸からきいきいという音が聞こえてくる。掛け軸を見てみると、描かれた水辺のサギが慌てて脇へ逃げ出す様子であった。そしてボートに乗った、亡くなったはずの高堂が現れる。高堂は綿貫に、庭のサルスベリがお前に懸想をしている、と言う。
_どうした高堂。
私は思わず声をかけた。
_逝ってしまったのではなかったのか。
_なに、雨に紛れて漕いできたのだ。
(中略)
_木に惚れられたのは初めてだ。
_木に、は余計だろう。惚れられたのは初めてだ、だけで充分だろう。
(中略)
木に惚れられたときにどうすべきか、またどうしたいのか、まるで思いもしないことだった。
夜中に掛け軸から亡くなったはずの人が現れても、まったく動じない綿貫。さらには庭のサルスベリに惚れられても、そんなこともあるのだな、という風で、むしろそんなサルスベリと真面目に向き合おうとする。
終始このようにクスリと笑えるような調子で、物語の時は流れていく。
河童が現れたり、白木蓮がタツノオトシゴを孕んだり、普通の日常では理解のできないことばかりが起きる中で、分からないけれど受け入れようとする綿貫の感覚が、いいなぁとしみじみ思わせる。
百年前の暮らしでは、人々はこうした日常と一続きになった不思議を、ごく自然に受け入れていたのかもしれない。
綿貫をからかうような高堂のキャラクターもよい。彼のおかげで、読み手には綿貫の人の好さがより伝わってくる。
飼い犬ゴロー
「都わすれ」という一編で一匹の犬が登場する。
雑誌の稿料で肉を買ってきた綿貫。肉の包みをさげて歩いていると、犬が後をついてくる。そのまま家の庭までやって来た犬を、再び掛け軸からどっこいしょと出てきていた高堂が、ゴローと名付ける。こうして綿貫はゴローを飼うことになった。
このゴロー、人間の言葉も良く理解できて、小さい体に男気あふれる性格が、なんとも可愛らしい。
山寺の和尚に、河童を滝壺まで届けるように言われると、自分が役に立つときが来たと心得て、わんと叫んで引き受ける。
また、隣のおかみさんは相当な犬好きで、綿貫の窮乏も知っているので、鶏肉の煮物など、おすそ分けを持ってきてくれるようになる。(ゴローのごはん、という体で)
おかみさんが、小さい時の高堂は、犬を飼いたがっていたが、父親が犬嫌いで飼えなかったと話す。それで高堂は、おかみさんがその頃飼っていたゴローという犬をかわいがっていたという。
それを知った綿貫は、ゴローに鶏肉を半分分けてやり、庭に咲いた都わすれを摘んで、床の間の掛け軸の前に飾る。
そうか、高堂、おまえは、この家でゴローを飼いたかったのだな、と声を出さずに呟いた。
季節は巡る
ネタバレしないように書くが、物語のラストで、なぜ高堂がこの世からいなくなってしまったのかが分かる。
そして綿貫は、もうこの世で会うことのできない友人にこう尋ねる。
_未だかつて見たことのない場所を、文筆によって表すにはどうしたらよいのだろうか。おまえのいた湖の底を書いてみたいと思うのだが。
綿貫のこの疑問は、文章(特に小説)を書く全ての人にとって、永遠のテーマなのではないだろうか。
現代では「無いもの」とされてしまっているような、不思議なのも、言葉で説明できないものたちは、確かに存在するのだろう。それらは、けっして遠い場所にあるのではない。日常に溶けあった、あの世とこの世のあわいのような、ふと道端を見ると咲いている小さな草花の間などにあったりするように思う。
亡くなった人も「私」をそばで見守っているし、もののけたちも、ただ怖いだけの存在ではない。
綿貫のような(ひいては梨木香歩のような)物書きがいるおかげで、わたしたちはそうしたことに気が付けるし、現代社会においても、あらゆることに寛容な、優しい心を忘れることなくいられるのだ。
果たして高堂は、何と答えたか_
まとめ
百年は、あっという間に経つ。
本書を開くと、わたしたちはすぐに明治20年代頃の、木々や草花の匂いたつ美しい庭付き二階家の中に移動している。そこには物書き兼「家守」の青年と、可愛い犬がいる。
「読書」の素敵なところは、いつだって、彼らの暮らす不思議な家にお邪魔して、「家守」体験ができること。
このブログは、カモメちゃんが「本はファッションの一部」を座右の銘に、自分らしさを伝えるツールとしての、「本」の楽しみ方をシェアする記事を書いています。面白い!と思ってくださった方は、ぜひ、ブックマークしてくださいね!